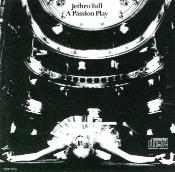
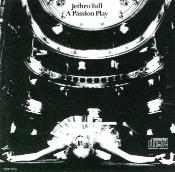
Music and lyrics by Ian Anderson except "The Story Of The Hare Who Lost His Spectacles" by Jeffrey Hammond-Hammond John Evan and Ian Anderson
Arranged by JETHRO TULL
Engineer: Robin Black
IAN ANDERSON: Vocal,Acoustic Guitars,Flute,Soprano and Sopranino Saxophones
MARTIN BARRE: Electric Guitar
JOHN EVAN: Piano,Organ,Synthesizer,Speech
JEFFREY HAMMOND-HAMMOND: Bass Guitar,Vocal
BARRIEMORE BARLOW:Drums,Timpani,Glockenspeil,Marimba
(Produced by Ian Anderson)
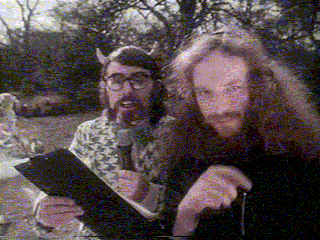 "The Story of the Hare Who Lost His Spectacles"のワンシーン。
"The Story of the Hare Who Lost His Spectacles"のワンシーン。




 -- Highly Recommended !
-- Highly Recommended !
 私的アオリ
私的アオリ
JETHRO TULLはフランスのエルヴィユ城(Le Chateau d'Herouville)にてニューアルバムのレコーディングに取り掛かるが諸般の理由によりボツとなる。(ボツテイクは「CHATEAU D'ISASTER TAPES」と名づけられ、「NIGHT CAP」で日の目を見る。詳細な経緯は「NIGHT CAP」に譲る。)
仕切りなおして新たにレコーディングされ、1973年にリリースされた本作は、「THICK AS A BRICK」と同じくたった1曲のみで構成されたトータルコンセプトアルバムである。全英第13位、全米第1位とセールス的にはビッグヒットとなったが、そのあまりに難解な内容からファンの間でも「最高傑作」と「退屈」で評価が真っ二つに分かれるまさに問題作だ。
Mobile Fidelity Sound Lab(MFSL)盤では16のパートに分かれているが実質的にはやはり1曲。前作とともにTULLの創作面・セールス面でのピークとされる本作のストーリーはロニー・ピルグリムなる男性の死後の人生ということらしい。
"A Passion Play"とは本来ならばキリスト受難劇のことであるが、死後の人生というストーリーにあわせるためモチーフを借りたというところだろう。
また、中間部にストーリーと無関係な小劇をはさむという構成も本来はキリスト受難劇のものである。
サウンドも歌詞の内容を反映してかヘヴィでダークだ。前作ではアコギの軽やかな弾き語りが45分という大作を飽きさせず引き締めていたのであるが、本作はこれでもかというばかりに攻撃的である。アコギの弾き語りは暗く緊張感を内包し、フルートの軽やかな調べは影を潜めサックスを多用してアヴァンギャルドな音を構築している。ハモンドがナレーションを取る中間部のルイス・キャロル風小劇"The Story Of The Hare Who Lost His Spectacles"にしても気安めにもならない。ここだけ比較的分かりやすい歌詞なのだが、笑い話のはずなのにサウンドが笑わせてくれないのだ。
笑い話といえばここ日本ではTULLを「演劇的」と評する声が多いが、TULLが本当に「演劇的」だったのは本作を挟む数年間である。こういった評価が一般化してしまった背景には、TULLがこの時期にセールス的なピークに達し来日も果たしたことが大きいと思われ、結局この評価がJETHRO TULLを近寄りがたい‘難解’なバンドとし日本でマイナー化させる要因の一つとなったというのが筆者の意見であるが、この「演劇性」を支えた重要なメンバーとしてジェフリー・ハモンドを挙げたい。
前作「THICK AS A BRICK」のブラックユーモアたっぷりのジャケもアンダーソンとハモンドの手になるものであったし、この時期のライヴを聴くとハモンドはMCやヴォーカル(!)まで担当しており、前述のように"The Story Of The Hare Who Lost His Spectacles"でもナレーションを担っていることなどから、この時期のアーティスティックな面でのクリエイティヴィティにおけるアンダーソンと並ぶ最重要人物は彼なのではないか、と筆者は考える。(Theatre Programmeによれば主人公ロニー・ピルグリムを演ずるのはマックス・クオッドことジェフリー・ハモンドである。)
曲は45分にわたって展開に展開を重ねる。一部繰り返されるテーマ(リフ)があるが、基本的には進むに従いハードに、偏屈になってゆく。前半のクライマックスは、「CHATEAU D'ISASTER TAPES」の生き残りでさらにハードなアレンジが施された7(Critique Oblique)だ。後にライヴバージョン(1974年パリ)が"Passion Play Extract"として「25周年BOX」に収録されることになる。
後半のクライマックスはラストのプログレハード、15(Magus Parde)にとどめを刺す。メタリックなギターリフ、奇天烈なリズムアレンジ、そしてサックス、フルート・・・ここにこの時期のJETHRO TULLの全てが凝縮されている。
このアルバムは確かにとっつきにくいが、我慢して、ここまで聴いてほしい
「THICK AS A BRICK」がコンセプトアルバムのパロディ的側面を持っていたのに対し、このアルバムは音だけとれば徹頭徹尾生真面目に「コンセプトアルバム」だ(Theatre Programmeの方はユーモアたっぷりなんだが)。45分1曲という曲構成は一見同じだが楽曲に対するアプローチは全く違う。これだけコマーシャリズムを排しながら全米第1位というのは凄いが、別にこれはアメリカ人が特に知的な国民というよりは(失礼!)、当時のアメリカでのTULLの人気の高さによるものであろう。
英国では13位止まりとなり、コンセプトのみならずフィルムとの一体をはかったコンサートもほとんどの評論家から酷評されることになった。
このアルバム、やはりファンの間でも好き嫌いが分かれるようで私個人はTULLのアルバムの中ではフェイヴァリットなのだが初心者にはやはり薦められない。長い曲でも大丈夫という人や変拍子がたまらないという方や暗ければ何でもよいという御仁はどうぞ買って下さい。理解するまで結構時間がかかると思われますので、慣れるまで繰り返し繰り返し繰り返し愛聴すること。15(Magus Parde)に入るときのマーティン・バーのギターリフの切り込みに無上の恍惚感を憶えるようになったとき、あなたはこのアルバムから離れられなくなるでしょう。
リマスター盤はエンハンスト仕様となっており、当時ライヴで使用された"The Story of the Hare Who Lost His Spectacles"のフィルムと、アナログ盤に付属していたTheatre Programmeの画像が付いている。
「A PASSION PLAY」のライヴは、フィルムと演奏の融合を狙ったものだったという。(ブートビデオが出回っているが画質劣悪で良く分からない。体験者の報告求ム!)
「A PASSION PLAY」の中間部分に映像を付けた形のこのフィルム - 厳密には"The Story〜"だけでなく、前後の"Forest Dance #1""Forest Dance #2"も含む - は、当時ライヴにて放映されたものらしく、「25周年ビデオ」にて既出である。「A PASSION PLAY」本編とは全く関係ないナンセンス小劇で、明らかにルイス・キャロルの影響下にあるが、英国的というかなんというか・・・説明しづらい。
ジェフリー・ハモンドがナレーションを務め、バレリーナや着ぐるみの動物たちがストーリーを織り成す。イアン・アンダーソン(監督役?)とバリー・バーロウ(カメラマン)がちょこっとだけ出ている。(マーティン・バーは発見できない。まさか、着ぐるみの中か・・・?)
音が若干アルバムバージョンと違っており、最初の"Forest Dance #1"にて、バレリーナが"Something wonderful is happening."とつぶやく。また中間部のシンセのブリッジがない。(これはリマスター前のCDがそうだった)
あと、ラストにジェフリー・ハモンドが去ってゆくシーンは「25周年ビデオ」にはなかった。
このころのアンダーソンはとにかくフィルム(映画)にこだわっていたようだ。次作「WARCHILD」では本気で映画製作をもくろむことになる。
アナログではもっともらしいプログラムが付属していた。リマスター盤ではジャケ内にもあるが、PCで再生すればデジタル画像を拝める。
このブックレットによれば"A Passion Play"は一つの劇でありきちんと役者が割り振られていて、リンウェル劇場(実在は不明)にて上演されることになっている。(もちろん内容が全部ウソッパチだということは読めば分かる)
そしてそれぞれの役者のプロフィールと写真が付いているのだが、これ、メンバーである。"Mark Ridly"なる人物はイアン・アンダーソン、"Derek Small"はマーティン・バー、"Max Quad"はジェフリー・ハモンド(この人が主人公みたい)、"John Tetrad"と"Ben Rossington"は判別しがたいがおそらく前者がバリモア・バーロウ、後者がジョン・エヴァンだと思われる。それぞれのプロフィールが全くの架空でないところにニヤリとさせられる。(分かったらマニア)
スタッフの名前などもクレジットされているのだがどうせほとんどが架空の人物かあるいは内輪な友人の名前であろう。少なくともテリー・エリスはマネジャー。
曲とは違ってこっちはブリティッシュユーモアたっぷりである。きちんとバランスを取ってるのね。おそるべし、イアン・スコット・アンダーソン。
 リンウェル劇場では禁煙とのこと
リンウェル劇場では禁煙とのこと
 戻る
戻る
j-tull.jp